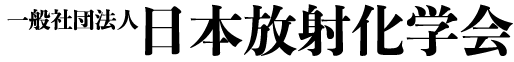JNRSメールニュース 第5号 (2016/02/02)
目次
- (5−01)
- 113番元素の命名権、日本へ!
- (5−02)
- P&Aのための錯形成剤TPEN誘導体の開発研究-日本化学会速報誌のハイライト論文として掲載
- (5−03)
- 宇宙線ミュオンで探る原子炉の溶けた核燃料
- (5−04)
- 放射線教育=科学教育+社会教育 -日本化学会・近畿支部 化学教育サロン-
(5-01) 113番元素の命名権、日本へ!
IUPAC(国際純正応用化学連合)は2015年12月30日に原子番号113,115,117,118の元素の発見と同定についての報道発表を行った。これが、12月31日早朝、IUPACから森田氏に伝えられた。113番元素に関する発見の優先権が理研グループ(単独)に与えられるという内容のものであった。その日の夕方に理化学研究所で記者会見があり、アジア初の元素命名権獲得のニュースが日本中を駆け巡った!
新元素発見の優先権については、新元素を発見したグループにIUPACが要請し、それに応じて提出された論文について、IUPACとIUPAP(国際純粋応用物理学連合)から選ばれた5名の専門家グループ(Joint
Working Party, JWP)によって審査される。
2012年の4月に新元素の発見者候補へのコールがあり、2012年5月31日がその締切であった。理研グループの基になった最初の論文は、2004年10月15日発行の日本物理学会の論文誌に掲載されたものであり、いわゆる冷たい融合反応である209Biに70Znを照射して113番元素を合成したとするものである。一方、オガネシアンをリーダーとするロシア・ドブナのグループは243Amに48Caを照射して115番元素を合成し、その娘核種が113番元素であるというものであり、その最初の論文は2004年2月2日発行の米国物理学会の論文誌に掲載された。もし両方のグループとも新元素発見の条件を満たしているならば、ドブナグループの方がわずかに早く発表したことになり、優先権はドブナグループに与えられることになる。
原子番号113,115,117,118の元素発見に関してのJWPからの最終報告が、IUPAC Technical Reportsとして2016年1月21日にオンライン版で発表された。このレポートを簡単にまとめる。理研グループの最初の崩壊連鎖のデータは、次に報告した崩壊連鎖のものと類似しているが、一部異なっていることから、新元素発見の条件を満たしているとは言えないとされていた。2006年、Qinらによる243Am(26Mg,3n)266Bhの測定、さらに、2009年、理研グループの248Cm(23Na,5n)266Bhの合成により、266Bhが崩壊連鎖の中での錨(anchor)となる既知核であると確立された。そして、2012年、278[113]からよく知られている258Lrまでの崩壊連鎖が観測され、新元素発見のための条件をすべて満たしたことになった。
一方、ドブナグループは243Am(48Ca,3n)288[115]の娘核種として284[113]を発見したとするものである。同じ核種が後の実験によって繰り返されデータの補強はなされたが、既知の原子核にも届いてもいなければ、交差反応でも確認されていないので、決定的な原子番号の同定ができていない。また、最終生成物であるDbに関する化学分離に関しては、まだ確固たる同定とはまだなりえない。以上より新元素発見のための条件を満たしていないとされた。
(HK)
(5-02)P&Aのための錯形成剤TPEN誘導体の開発研究-日本化学会速報誌のハイライト論文として掲載
標題の研究は、日本化学会の欧文速報誌,Chemistry Lettersに書かれたハイライト論文[1]である。東工大竹下先生のグループ、神戸大学森先生のグループ、JAEA
SPring8の矢板グループが共同で行ってきた研究開発をまとめたものである。論文には、示されていないが、吸着剤の合成は森グループ、吸着性能の評価は竹下グループ、構造解析は矢板グループが行っている。
この研究の背景から説明を行う。 “Introduction”に書かれているように、原子力利用で発生する高レベル廃棄物の地層処分の時間を制御する方法として分離・核変換(partitioning & transmutation:
P&Tと約す。) と言う概念が提案されている。P&Tは長半減期の放射性核種を高レベル廃棄物から取り出して、半減期の短いものに核変換する技術である。P&Tの具体的な対象はAm-241であり、高レベル廃棄物中のランタノイドとAmを分離することが必要になる。ランタノイドを分離するのは、中性子捕捉断面積が大きく、核変換に使う中性子を無駄に消費するからである。3価のアクチノイドとランタノイドはf軌道に由来する電子構造やイオンサイズが似ていることから分離が難しいとされている。この両者の分離のために世界中で様々な試みがされているが、ソフトドナー配位子を用いたものが期待されている。このハイライト論文においてはソフトドナー配位子開発研究として、窒素ドナーの6座配位子である錯形成剤
N,N,N’,N’-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylendiamine (TPEN) 誘導体を用いた成果がまとめてある。
TPEN誘導体のソフト性はCd(II)の硝酸溶液中での吸着で評価している。吸着性能ではpH依存性について評価している。TPEN誘導体としては、水溶液への溶解を抑えるためピリジン環に種々の側鎖をつけたもの、吸着特性を変えるためピリジン基の代わりに6員環中の窒素が2つあるピラジンや窒素が3つあるトリアジンにしたもの、ピリジン環を繋ぐエチレンジアミンのエチレンの部分をより長いアルキル鎖に代えたものが試験されている。さらには、温度反応性ゲルであるPoly-N-isopropyl-acrylamide
(NPA) にTPENを取り付けて分配係数を温度で変化させた結果なども示されている。また、構造解析では、EuおよびCuとの錯体の結晶構造が調べられており、報告されている。
本論文は、種々TPEN誘導体の合成とその吸着特性変化が示されているが、実際に高レベル放射性廃棄物中のAm分離に応用するには、更なるデータを取得する必要があるだろう。
[1] Yuji Miyazaki, Shinichi Suzuki, Toru Kobayashi, Tsuyoshi Yaita, Yusuke
Inaba, Kenji Takeshita, and Atsunori Mori, “Synthetic Design of TPEN
Derivatives for Selective Extraction of Trivalent Minor Actinides against
Lanthanides” Chem. Lett. 44(2015)1626-1636.
(TS)
(5-03) 宇宙線ミュオンで探る原子炉の溶けた核燃料
GeV領域の高エネルギーを持つ宇宙線が地球の大気と衝突し、極短寿命のパイオン(π+/π-)を経てミュオン(μ+/μ-)が生成される。その電荷は電子と同じで質量が電子の約200倍であるため高い透過力を持つ。その透過力は物質の密度に依存し、その量は地表では10,000個/m2/minほども有り、宇宙線ミュオンを用いて小さな物から巨大な物までのトモグラフィー、いわゆるレントゲン撮影が可能となる。
1950年代にE.P.Georgeが地中の坑道の撮影に成功し*1)、1970年にはL.W.Alvarezによりピラミッドの隠し部屋の調査が行われた*2)。日本では東京大学の永嶺や田中により火山の内部の観測が行われている*3)。数m長のプラスチックシンチレータを縦横に複数並べたポジションセンシティブな平面検出器を垂直に立て、それらを何台か平行に並べることによってミュオンの飛来方向を観測し、火山の内部構造のイメージングに成功しており、薩摩硫黄岳や浅間山の噴火予知などの研究に役立てている*4)。
この方法を福島第一原子力発電所の、原子炉の内部の極めて線量率の高い、溶け落ちた核燃料などの状況の把握に応用しようという試みがスタートしている。
KEK、筑波大、東京大、首都大のグループは火山の場合と同様にプラスチックシンチレータを並べたホドスコープを3式用い、透過画像を再構築することによる3Dイメージング法を開発しており、停止中の日本原子力発電・東海第2発電所において実証試験を行っている*5)。
名古屋大学では、検出器に軽量・コンパクトな厚さ0.3mmの乳化AgBrの写真乾板を用い、乾板上の軌跡の直線性や長さから、ガンマ線によるものとミュオンによるものとの弁別が可能であり、100m先を10cmの精度で観測可能としている*6)。
(株)東芝とIRID*7)では、ミュオンの散乱角が原子番号に比例することを利用して、測定対象の前後に検出器を置いて散乱角を測定し、これまでの透過法と組み合わせることにより物質の識別を可能としている*8)。測定器はアルミ筒のガス検出器である安価・頑丈なドリフトチューブ検出器で、ミュオンによるガスの電離を観測することにより位置分解能0.4mmを実現し、これを多数並べて7m×7mの検出器として、これを2基用い、東芝研究炉によるシミュレーションを含めた実証試験を行っており、数ヶ月間の測定で30cm程度の位置分解能で透視可能としている。2016年には停止中の福島第2発電所での実証試験を予定している。
一方で、大阪大学、KEK、 JAEA、北大、国際基督教大、首都大、JAXAなどはJ-PARCミュオン施設を用いてミュオンが物質に当たって生成される特性X線を観測することにより、数mmの厚さの隕石中の軽元素C、B、N、Oなどの非破壊分析に成功している*9)。この方法を加速器に比べて1,000倍高エネルギーな宇宙線ミュオンに適用することが出来れば、さらに厚い対象物も観測出来る可能性が考えられ、これまでの宇宙線ミュオンの透過法や散乱法によるトモグラフィーを「白黒」とすれば、それらと組み合わせることにより「カラー化」されることとなり、より多くの情報を引き出すことが可能になると期待される。
備考、参考文献
*1): Cosmic rays measure overburden of tunnel, E.P.George, Commonwealth
Engineer, 455,July 1,1955.
*2): Search for hidden chambers in the pyramids using cosmic rays, L.W.
Alvarez et al., Science 167(1970)832.
*3): 宇宙線ミュオンによる火山内部探索, 永嶺兼忠、田中K.M.宏幸, 火山 48,4,345-366, 2003.など.
*4): 特集「素粒子で地球をのぞく」, 東京大学地震研究所ニュースレターNo.2.
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2014/05/eri_nlp_2.pdf など.
*5): 宇宙線ミュオンを用いた原子炉の調査, KEKプレスリリース, 2014年1月23日.
https://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20140123110000/
*6): 名古屋大学が(株)東芝と共同で、福島第一原子力発電所2号機原子炉内部の宇宙線ミュー粒子による透視に成功, 名古屋大学Press Release.
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20150320_esi.pdf
*7): 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構
International Research Institute for Nuclear Decommissioning
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた研究を行う団体。2013年8月に、日本原子力研究開発機構や沖縄電力を除く電力会社、プラントメーカーなど18法人により設立された。略称はIRID(アイリッド).
web siteはhttp://irid.or.jp/
*8) : 宇宙線を用い福島第一原子力発電所の燃料デブリの状態を測定する装置を開発, (株)東芝:プレスリリース.
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_03/pr_j2701.htm
*9): 人類が手にする物質を透視する新しい“眼”- 素粒子ミュオンを使った非破壊軽元素分析に成功 -, J-PARCセンター プレス発表, 2014年5月27日.
https://j-parc.jp/ja/topics/2014/Pulse140527.html
(YW)
(5-04) 放射線教育=科学教育+社会教育 -日本化学会・近畿支部 化学教育サロン-
2015年10月10日(土)大阪教育大学で、日本化学会近畿支部主催の第20回化学教育サロン「放射線教育の今とこれからを考える」が開催された。このサロン(パネルディスカッション)の目的は、3.11福島の原発事故を機に、問われ続けている理科教育における放射線教育の現在のあり方を議論し、これからの充実をはかるとことにあった[1]。参加者は学生、中高教諭、大学教員で、総数23名という。
4人のパネリストは、物理学者、化学者、教育学者、中学校教諭であったが、化学者は、本会会員である京都大学原子炉実験所の高宮幸一氏が務めた。高宮氏は「放射線教育には科学教育と社会教育の側面があり、科学教育的には、物理、化学との様々な単元と関連をもたせ、社会教育的には、科学的な理解を準備して社会的な影響を考える必要がある」と提言した。至言である。
高宮氏によれば、物理学者でありながら積極的に社会教育を実践されている坂東昌子氏の熱意は素晴らしいもので、様々な経験を通して語られた講演から、社会教育の中で科学者がどのような役割を果たすべきかを考えるためのヒントが得られたとのことである。また、会場からは多くの質問やコメントがあり、参加者の方々の放射線教育に対する意識の高さが伺えたが、参加者数はこれまでに開かれた化学教育サロンに比べると非常に少なく、教育を行う側からは敷居の高い分野であることがあらためて感じられたという。
[1]村上忠幸; 化学と教育、64巻、41(2016)
(YS)